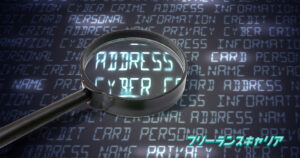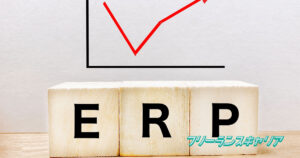プロジェクトのスムーズな推進のため、特にシステム開発の初期フェーズでは「要件定義」と「要求定義」が欠けてはならない重要なステップです。しかし、これら二つの意味は非常に近いため、混同してしまうことも少なくありません。今回は、「要件定義」と「要求定義」の違いを明確に理解し、適切に活用するためのポイントを解説します。
要件定義とは
まずはじめに、要件定義についての理解を深めていきましょう。
要件定義とは、システムや製品が必要とされる機能や性能、制約条件を、開発の目指すべきゴールとして明確に定義する作業のことを指します。このステップで重要なのは、製品やシステムが満たすべき要素を厳正にリストアップし、それらを整理・公式化することです。これにはユーザーの要求だけでなく、法規制や安全基準、業界の標準など、外部からの要請も含まれます。要件定義が適切に行われないと、後の設計や開発フェーズで混乱やミスが生じる可能性があります。
要求定義とは
次に、要求定義について解説します。
「要求」は「求める」という動詞性からもわかるように、その名の通り「ユーザー」または「顧客」の要求をとらえ、それを明確に定義する作業のことを指します。製品やサービスを設計・開発する上で最も重要なのは、その製品やサービスを使うであろう「ユーザー」の視点を理解することです。ユーザーが何を望み、何に困っているのかをしっかりととらえることが、良質な製品やサービスを生み出す初めの一歩となります。その結果、どのようなシステムや製品を開発すべきか、その全体像や細部の要素を特定するという具体的な方向性を示す役割を果たします。
要件定義と要求定義の違い
要件定義と要求定義は、ともに開発するべき製品やシステムの定義を行うという点では共通しています。しかし、明確に区別する必要があります。大きな違いは、要件定義が外部からの要請も含め「何を満たすべきか」、全体のゴールを示すためのものである点です。一方、要求定義は、「誰の何を満たすべきか」を示し、具体的な要素を洗い出すためのものである点です。言い換えれば、要求定義はユーザー中心の視点で、具体的な要素を洗い出す作業です。
要件定義と要求定義をどう使い分けるか
では、要件定義と要求定義をどのように使い分ければ良いのでしょうか。まずはじめに、ユーザーのニーズを深く理解するために要求定義を行い、具体的な要素や全体像を洗い出します。その結果を基に、開発すべき製品やシステムの要件を決定する要件定義に進みます。この両者は、一方が上位で他方が下位、といった単純な関係ではなく、両者が相互に補完し合いながら開発プロジェクトを進めるための重要なツールであると考えるべきです。
ファシリテーションの重要性
要件定義と要求定義の違いを理解し、適切な使い方をするためには、ファシリテーションの技術が非常に重要となります。お客様やユーザーとのコミュニケーションを深め、ニーズを正確にとらえるためには、適切な質問力やリスニング力が求められます。また、様々なニーズを統合し、共通の理解を図るためのナビゲーション能力も必要となるでしょう。さらに、要求定義と要件定義の間には、多くのバイアスや誤解が存在する可能性もあります。そのため、赤裸々なコミュニケーションと全員の受け入れの先に、真の解決策が見つかると言えるでしょう。
要件定義を進める際のポイント

要件定義を進めるためには、3つのステップを踏むのが基本的です。
ここでは、顧客や利用者からの要望を聞き出します。具体的に何を求められているのか、その要望を満たすためにはどのような機能や性能が必要なのかを詰めていきます。
ここでは、提出された要求が実際のところ技術的に可能なのか、コスト面で適切なのか、また、その要求によって提供可能な価値が予期したものであるかなどを要求仕様をもとに検証します。この過程で、要求が曖昧だった場合や、新たな要求が発生した場合もあるので、その度に顧客や利用者と連携を取りながら修正を行っていきます。
ここまでの過程で明らかになった要件をもとに、具体的なシステムの仕様や操作方法などを明記します。これが設計や実装のための具体的なガイドラインとなります。
ポイント1:明確なゴール設定
要件定義を進めるうえで重要なポイントの一つは、明確なゴールの設定です。具体的に何を達成したいのか、どのような問題を解決したいのかを明確にすることで、具体的な機能や性能の要件が見えてきます。
ゴール設定を行う際には、
SMART原則
・具体的(Specific)
・測定可能(Measurable)
・達成可能(Attainable)
・現実的(Realistic)
・時間制限あり(Time-bound))
に基づくとより良くなるでしょう。SMART原則に基づく目標設定は、具体性を持ちつつも現実的な範囲に収めることを重視しています。これを活用することで、達成可能なゴール設定が可能となり、そしてその結果として要件定義の精度を向上させることができます。
ポイント2:利用者視点の考慮
要件定義では、「利用者視点」を意識した取り組みが必要不可欠です。システムの完成形を思い描く上で、そのシステムを実際に利用するユーザーの視点やニーズをどれだけ汲み取ることができるかが重要となります。
具体的には、可能であればユーザーインタビューを行い、彼らの日々のタスクや問題点を理解します。そして、そこから洗い出されたユーザーのニーズや問題をどう解決するかを考えることで、ユーザーセンタリックなシステム設計が可能となるでしょう。
ポイント3:フレキシブルな姿勢
要件定義の過程で新たな情報が出てきたり、要件が変更されることもあります。そのような変化に対して柔軟に対応し、フレキシブルな姿勢を持つことが重要です。ただしフレキシブルさというのは、無秩序に全ての要求を受け入れるという意味ではありません。
新たな要求や情報が出てきた場合、その要求に応じたコストや時間、リスクなどを評価し、全体のゴールやプロジェクトの実情に照らし合わせて、論理的に判断することが求められます。良い要件定義とは、このように変化する要求や情報に対して、適切に修正や更新を行うことができるものと言えるでしょう。
要求定義を進める際のポイント

続いて要求定義を進めるポイントについてみていきましょう。進め方としてはまずはじめに、顧客からの情報を収集するためのミーティングを通じて、それぞれが抱えている問題それ自体を明白にすることから出発します。ミーティングを通じて相手から情報を得るだけでなく、自分たちの側からも質問を投げかけ、クライアントが本当に必要としているものを探り出す作業が進められます。
このビジネスの背景や問題点、目的といった内容を、丁寧に洗い出していくのが大切です。具体的なシステムの設計や開発に入る前に、しっかりと目的と要望、問題を把握しておくことで後の工程がスムーズに進むためです。
ポイント1:顧客視点に立つ
要求定義のポイントとしてまず挙げるべきは「顧客視点に立つ」ことです。
自分たちが考える技術的な面白さや完璧さを追求するだけではなく、目の前の顧客が何を望み、何を必要としているのかを常に考えるべきです。サービスやシステムを作る上で一番重要な要素は、それが顧客の問題解決に役立つかどうかなのです。
ポイント2:明確な文書化
次に重要なのが、要望や要件を「明確に文書化する」ことです。
口頭での説明だけでなく、紙面にしっかりと要求をまとめ、それを顧客やチームと共有することです。考えを文字にすることで、更に理解を深めることが可能になる一方、他のメンバーとの情報共有や、後で見返した際のベースとなります。明確な文書作成はマストな考え方と捉えてください。
ポイント3:アイデアのブレインストーミング
最後のポイントは、「アイデアのブレインストーミング」を積極的に行うことです。
各メンバーから色んな視点での提案を引き出し、全体の中からより良い解決策やアイデアを探り出す方法です。これによって一見距離のある異なる意見が、新たな解決策を生むきっかけになったりします。
まとめ
要件定義と要求定義、これらはシステム開発では不可欠なフェーズであり、混同しがちな概念ではありますが、その違いをしっかり理解し、効果的に組み合わせて使うことで、成功に繋がるシステム開発を進めることができます。ユーザーの真のニーズを探求する要求定義と、それを包括的にとらえ整理する要件定義、二つの違いを理解し、プロジェクトに活かしていきましょう。
また、案件獲得にはフリーランスキャリアの利用をぜひ検討してみてください。これまでの経験やスキルに応じた案件を紹介させて頂きます。