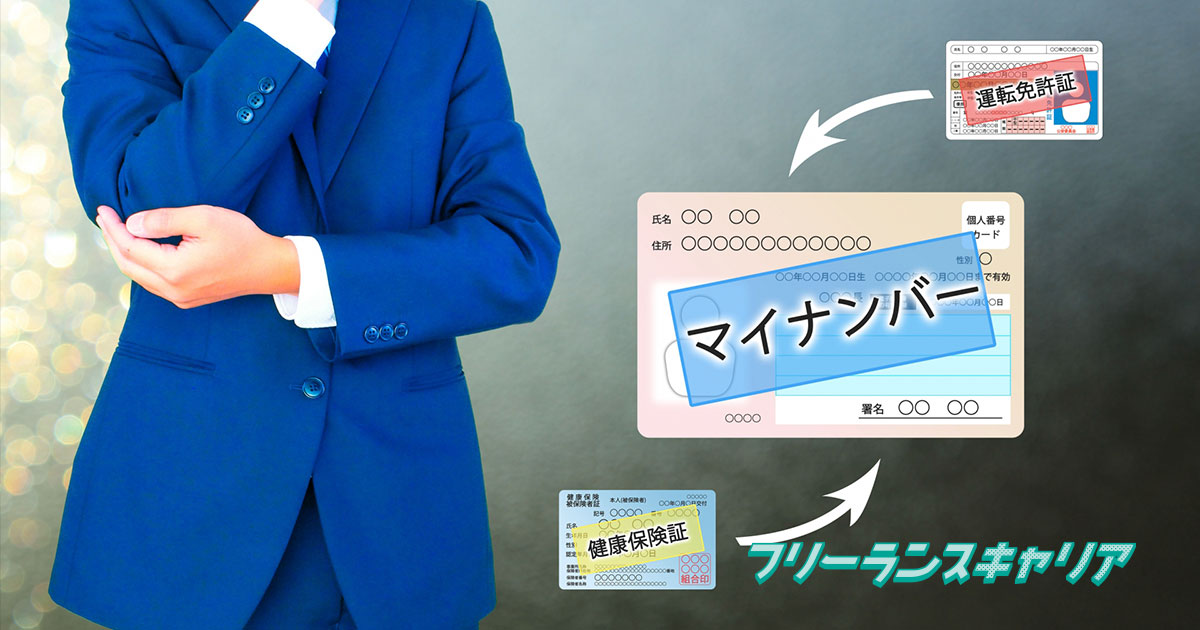フリーランスにとって、マイナンバーは切っても切れない存在です。確定申告や社会保障手続きなどに必要不可欠であり、適切に管理することが求められます。しかし、フリーランスならではの疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
例えば、

フリーランスでもマイナンバーは必要なの?



確定申告にマイナンバーが必要って本当?



発注者にマイナンバーを提供する際の注意点は?
などです。
本記事ではこうしたフリーランスの方々の疑問に答えるべく、マイナンバーの基本知識から取得方法、確定申告での取り扱い、発注者への提供、安全管理に至るまで、幅広い情報をお届けします。この記事を通じてマイナンバーについての理解を深め、フリーランス業務が円滑になれば幸いです。
マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を有する全ての人に割り当てられる個人識別番号です。2016年1月から導入されたこの制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、公平・公正な社会を実現するために欠かせません。具体的には、年金の資格取得や確定申告、医療保険の手続きなどで使用されます。
フリーランスの方も、原則としてマイナンバーを取得する必要があります。個人事業主は、税務署への届出や確定申告などでマイナンバーの提示が求められるためです。また、フリーランスが法人と契約する際、報酬の支払調書にマイナンバーの記載が必要なケースもあります。つまり、フリーランスにとってマイナンバーは、事業を営む上で欠かせない存在と言えるでしょう。
フリーランスのマイナンバー取得方法


では、フリーランスはどのようにマイナンバーを取得すればよいのでしょうか。基本的な流れは以下の通りです。
まず、住民票の住所地の市区町村からマイナンバーと氏名、住所、生年月日、性別が記載された「通知カード」が送付されます。受け取った通知カードは、大切に保管しましょう。万が一紛失した場合は、市区町村の窓口で再発行の手続きを行う必要があります。
次に、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得します。マイナンバーカードは表面にマイナンバーが記載され、裏面に顔写真などが掲載されているプラスチック製のICカード。これを取得すると、e-Taxでの確定申告や、コンビニでの各種証明書の取得などが可能になります。
マイナンバーカードの申請は、通知カードに同封されている申請書を郵送する方法と、スマートフォンやパソコンからオンライン申請する方法があり、市区町村の窓口でも申請できます。申請の際は、顔写真の用意が必要です。撮影した写真データをアップロードするか、写真店などで撮影した証明写真を添付しましょう。
申請は、できればオンラインをおすすめします。スマートフォンで顔写真を撮影し、必要事項を入力するだけで手続きが完了。約1ヶ月半後、自宅にマイナンバーカードが届きます。
確定申告とマイナンバー
フリーランスの確定申告書には、マイナンバーの記載が必須です。確定申告書の提出方法には、大きく分けて郵送と電子申告(e-Tax)の2つ。郵送の場合は、確定申告書にマイナンバーを記載し、本人確認書類の写しを添付しましょう。本人確認書類としては、マイナンバーカード、通知カード、運転免許証などが該当します。
一方、e-Taxでの申告では、マイナンバーカードを利用することで、添付書類が省略でき、スムーズに手続きを進められます。マイナンバーカードをICカードリーダーに読み込ませ、暗証番号を入力するだけで、本人確認が完了。昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、e-Taxの利用が推奨されていることもあり、マイナンバーカードの取得とe-Taxの活用は、フリーランスにとって大きなメリットと言えるでしょう。
発注者へのマイナンバー提供
フリーランスが仕事を受注する際、発注者からマイナンバーの提供を求められるケースも。これは発注者が税務署に提出する支払調書にマイナンバーの記載が必要な場合などに発生します。報酬額が一定の基準を超える場合、支払調書の提出が義務付けられているためです。
マイナンバーの提供方法としては、大きく3つあります。
どの方法を選ぶかは、発注者との協議で決めると良いでしょう。
ただし、マイナンバーは極めて重要な個人情報であるため、提供の際は細心の注意が必要です。不必要な提供は避け、提供先の情報管理体制を確認することが大切です。また、マイナンバーの提供記録を残しておくことも忘れてはいけません。
おすすめは発注者からマイナンバーの提供を求められた際、まずは提供の必要性を確認すること。その上で、マイナンバーカードのコピーを密封の上、書留で郵送すると良いでしょう。口頭での伝達は、トラブルを避けるためにも控えた方が無難です。マイナンバー提供の際は、慎重に対応することをおすすめします。
マイナンバーの安全管理
フリーランスは、個人事業主としてマイナンバーを適切に管理する責任があります。マイナンバーの紛失や流出は、本人の信用低下やなりすましなどのリスクにつながる恐れも。そのため、日頃からセキュリティ対策を講じることが重要です。
まず、マイナンバーが記載された書類は、鍵のかかる場所で保管し、必要以上に持ち歩かないようにしましょう。できれば自宅の金庫で保管すると良いでしょう。また、パソコンやスマートフォンにマイナンバーを保存する場合は、暗号化やパスワード設定が欠かせません。
さらに、マイナンバーを取り扱う業務を外部に委託する場合は、委託先の情報管理体制を確認し、適切な監督を行う必要があります。フリーランスとはいえ、個人情報保護法の適用を受けるため、法令順守は徹底しなければいけません。
万が一マイナンバーが流出した場合は、速やかに専用のコールセンターへ連絡しましょう。マイナンバーの変更は認められていませんが、警察や日本年金機構など関係機関への連絡と、不正利用のチェックなど必要な対応をサポートしてくれます。
フリーランスに関連するマイナンバー法律・規定
フリーランスは、個人事業主として「個人情報保護法」「所得税法」「国民健康保険法」など、様々な法律や規定の対象となります。
個人情報保護法では、マイナンバーを含む個人情報の適切な管理が求められます。また、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」にも留意が必要です。このガイドラインでは、マイナンバーの利用範囲や安全管理措置などについて詳細に規定されています。フリーランスはこれらを踏まえ、コンプライアンスを徹底することが求められます。
所得税法では、マイナンバーの記載が求められる支払調書や確定申告書の提出と、適切な納税義務の遂行が求められます。事業規模に応じて、地方消費税の申告納付や、源泉所得税の納付義務が生じる場合もあるので注意が必要です。
フリーランスは、国民健康保険や国民年金の被保険者となるケースが多いですが、その手続きにもマイナンバーの提示が求められます。社会保障関連の手続きでは、正確なマイナンバーの提供が不可欠だと言えるでしょう。
正しい知識を身につけ、マイナンバーと上手に付き合おう
本記事ではフリーランスの方々に向けて、マイナンバーに関する重要な情報を解説しました。マイナンバーはフリーランスにとって避けて通れない存在ですが、適切に管理し、有効活用することが大切です。
マイナンバーの取得から確定申告、発注者への提供、安全管理に至るまで、一つひとつ丁寧に対応していきましょう。また、法律や規定にも注意を払い、個人事業主としての義務を果たすことが求められます。
フリーランスのみなさんには本記事を参考に、マイナンバーと上手に付き合っていただければと思います。マイナンバーに関する最新情報は、内閣府のマイナンバー公式サイトや、国税庁のウェブサイトなどで随時確認することをおすすめします。
様々な手続きが煩雑に感じられるかもしれませんが、正しい知識を身につけ、一つずつ対処していけば、フリーランスの業務もスムーズに進められるはずです。みなさんが安心して働ける環境づくりをサポートできれば幸いです。
また、案件獲得にはフリーランスキャリアの利用をぜひ検討してみてください。これまでの経験やスキルに応じた案件を紹介させて頂きます。