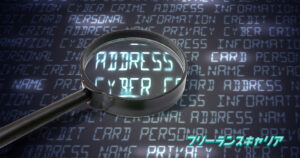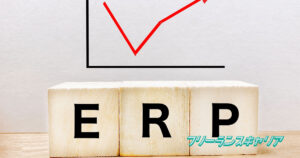IT化が進んだ昨今では、情報システムが重要な役割を果たしています。しかし、システムを導入するだけでは十分ではありません。システムを安定的に運用し、継続的に保守していくことが、企業の生産性を維持し、競争力を高めるために不可欠です。本記事では、システム運用・保守の基本概念から、具体的な業務内容、ポイント、課題と対策までを網羅的に解説します。安定したシステム運用を目指している企業のご担当者の方はぜひご覧ください。
システム運用・保守とは
システム運用・保守はシステムを安定的に稼働させ、ビジネス要件に適合するよう維持・改善していくための一連の活動。運用はシステムの日々の監視や制御、ユーザーサポートなどの業務を含み、保守はシステムの修正、更新、機能拡張などを行います。
システムのライフサイクルにおいて、運用・保守は開発フェーズの後に位置づけられます。開発が完了しシステムが本番環境に移行された後が、運用・保守のフェーズ。このフェーズは、システムの耐用年数が尽きるまで継続されます。
システム運用・保守の主な業務
続いてシステム運用・保守の具体的な仕事内容について詳しく見ていきましょう。
システムの安定稼働を維持するため、常時監視を行います。サーバーやネットワークの稼働状況、CPU使用率、メモリ使用量、ディスク容量などを監視し、異常があれば速やかに対処。システムのパフォーマンスを定期的に分析し、ボトルネックの特定と解消に努めます。
データ損失や災害に備え、定期的にデータのバックアップを取得します。バックアップ方針を定め、バックアップの頻度、保管場所、保持期間なども決定。リカバリ手順を文書化し、定期的に訓練を行い、緊急時に速やかにシステムを復旧できる体制を整えます。
システムを外部からの脅威から保護するため、セキュリティ管理を行います。ファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入、OSやソフトウェアの脆弱性対策、ユーザーアクセス制御、ログ管理などを通じて、システムのセキュリティも維持。定期的にセキュリティ監査を実施し、潜在的なリスクを洗い出します。
ユーザーからの問い合わせに対応し、システムの使用方法をサポートします。障害が発生した場合は、速やかに原因を特定し、解決に向けた対応も実施。問題の再発防止のため、根本原因を分析し、必要に応じてシステムの改善を行います。
システムを最新の状態に保つため、定期的にソフトウェアのバージョンアップやパッチの適用を行います。更新作業はシステムの可用性に影響を与えないよう、計画的に実施。更新によるシステムへの影響を事前にテストし、問題がないことを確認してから本番環境に適用します。
システム運用・保守のポイント

続いて、システム運用・保守を円滑に進めるためのポイントについて解説します。
運用・保守業務を効率的かつ確実に実施するため、手順を文書化します。手順書には作業の目的、手順、留意点などを詳細に記載。これにより作業の標準化が図られ、人的エラーの防止が可能に。担当者が交代しても、一定の品質を維持できます。
運用・保守業務には、定型的で繰り返し発生する作業も。これらの作業を自動化することで、効率化と品質向上が期待できます。監視やバックアップ、パッチ適用などの作業は、自動化ツールを活用することで、人的工数を大幅に削減できるでしょう。
定期的に性能レビューを実施しましょう。ボトルネックとなっている処理を特定したら、チューニングを行います。SQLの最適化、インデックスの追加、メモリの増設、ネットワークの高速化などを通じて、システムのパフォーマンスを最適な状態に維持できるはずです。
システム障害は、企業の業務に大きな影響を与えます。障害発生時に速やかに対応できるよう、障害対応計画を策定することも重要です。計画する際は、障害検知方法、連絡体制、対応手順、復旧目標時間などを定めます。定期的に計画の見直しを行い、最新の状況に適合するよう更新してください。
運用・保守業務は、高度な技術スキルを必要とします。要員のスキルを向上させるため、定期的な教育や訓練を実施。新しい技術や製品に関する知識を習得させ、業務で活用できるようにします。ベンダー資格の取得を奨励し、専門性を高めましょう。
システム運用・保守の課題と対策
最後にシステム運用・保守の課題と解決策について解説します。詳しく見ていきましょう。
企業のシステムは、年々複雑化・大規模化し、クラウドやマイクロサービスの導入により、システム構成も多様化しています。運用・保守チームは、これらの新しい技術に対応できるよう、スキルを向上させる必要があります。ツールの活用により、複雑なシステムを効率的に管理できるようにしましょう。
サイバー攻撃は年々巧妙化し、企業のシステムは常に脅威にさらされています。運用・保守チームは最新のセキュリティ動向を把握し、適切な対策を講じる必要があります。脆弱性管理、ログ分析、インシデント対応などの業務を通じて、システムのセキュリティを維持しましょう。
システム運用・保守のコストは、企業にとって大きな負担となっています。コスト削減のため、運用・保守業務の効率化が求められます。自動化やツールの活用、アウトソーシングの推進などにより、業務の最適化を図りましょう。クラウドを活用すれば、インフラコストも削減できます。
クラウドやAIは、システム運用・保守の分野でも活用が進んでいます。クラウドを活用することで、インフラの調達や構築に関する工数を削減できます。また、AIを活用することで、システムの異常検知や性能予測などの自動化も可能に。こうした新しい技術を積極的に取り入れ、業務の高度化を図る必要があります。
適切な投資と体制構築で、安定したシステム運用を
本記事ではシステム運用・保守の基本概念から、具体的な業務内容やポイント、課題と対策までを網羅的に解説しました。システム運用・保守は、企業のシステムを安定的に稼働させ、ビジネス要件に適合するよう維持・改善していくために不可欠な活動です。
運用・保守チームは、システムの監視、バックアップ、セキュリティ管理、ユーザーサポートなどを通じて、システムの安定稼働を維持するポジション。定期的な性能レビューやチューニング、障害対応計画の策定などにより、システムの最適化と可用性の向上も図ります。
今後のシステム運用・保守では、複雑化するシステムへの対応、セキュリティ脅威への対策、コスト削減と効率化が課題に。解決に向け、スキルの向上、ツールの活用、新技術の導入などが求められています。クラウドやAIの活用も、運用・保守業務の高度化に寄与するでしょう。
ビジネスで成功するためには、システム運用・保守の重要性を認識し、適切な投資と体制づくりを行うことが肝要です。経営層からの理解と支援を得て、強力なリーダーシップのもとで運用・保守を遂行できる環境が求められています。ぜひ本記事を参考に、安定したシステム運用・保守を実現してください。
また、案件獲得にはフリーランスキャリアの利用をぜひ検討してみてください。これまでの経験やスキルに応じた案件を紹介させて頂きます。