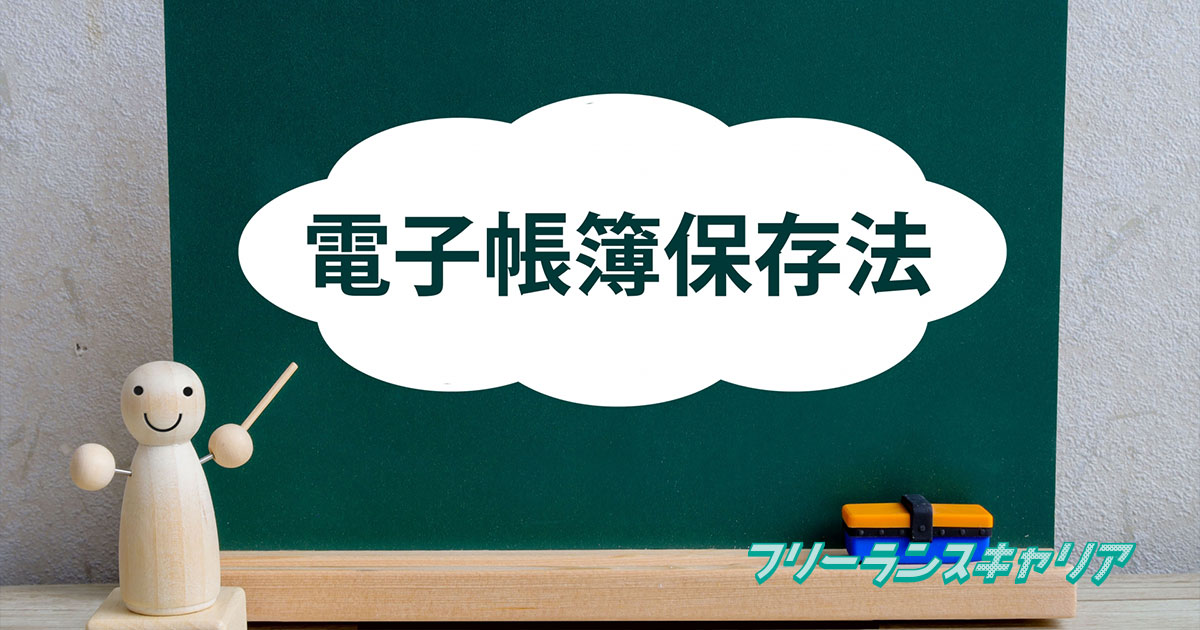2022年に改正された「電子帳簿保存法」の「電子取引データ保存」が2024年1月より完全に義務化されます。フリーランスにとって、またこれからフリーランスを目指している方も含めどんな影響がありどのような対応をすべきか詳しく解説していきますのでぜひ参考にしてください。
電子帳簿保存法とは?
「電子帳簿保存法」とは、正式名称「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の略で国税関係帳簿や書類等を電磁的記録(電子データ)で保存することを義務化する法律です。
「国税関係帳簿」とは仕訳帳、総勘定元帳、売上台帳、仕入台帳などの帳簿のことで、国税関係帳簿は国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないとされている帳簿です。
また課税事業者は帳簿を備え付けて、取引を行った年月日・内容・金額・相手方の氏名または名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、7年間保存しなければなりません。
帳簿などは多くの種類や形式があり紙で保存する必要がありましたが、電子帳簿保存法施行後は電子データでの保存もできるようになりました。
電子帳簿保存法の3種類の区分とルール
電子帳簿保存法は3つに区分してそれぞれルールを定めています。
電子帳簿保存法は、「電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存」する方法です。例えば会計ソフトで作成した国税関係帳簿や書類等をデータとして保存します。また自社が電子的に作成した請求書等の控えなども含まれます。
スキャナ保存法は、「紙の書類をスキャナやスマホで読み取り画像で保存」する方法です。取引先から紙で受け取った請求書や受領書など、自社で作成した紙の取引関係書類の控えも該当します。
電子取引データは、「電子データでやり取りした取引情報をデータ保存」する方法です。自社が発行した書類、取引先から発行された書類のどちらも該当します。
具体的には以下になります。
・電子メールで請求書や領収書などのデータの受領
・インターネットでPDFファイルをダウンロードした場合
・クラウドサービスでデータの請求書や領収書を受領した場合
フリーランスが電子帳簿保存法で得られるメリットやデメリットは?
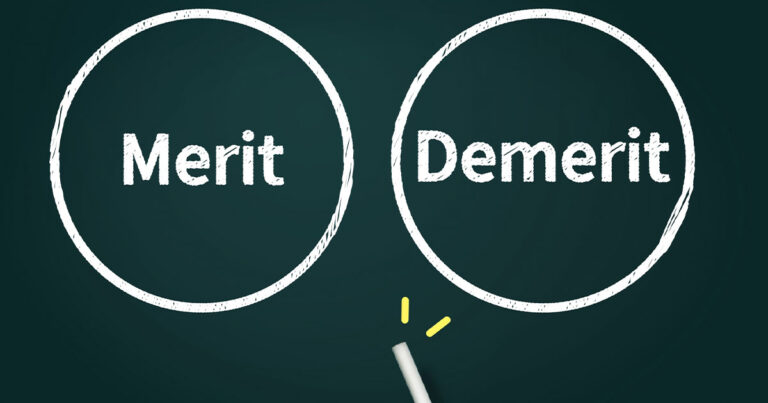
電子帳簿保存法によってフリーランスにはどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
【電子帳簿保存法のメリット】
電子データで帳簿や書類を保存することは書類の置き場の削減につながります。帳簿や書類は7年程度保管しなくてはならないものなので、紙での保管の場合は保管スペースの占有や外部委託で保管する場合には利用コストがかかるなど、データ保存はその分保管場所の確保やコストもかかららず効果的です。
紙の帳簿保管の場合にはファイリング作業が発生しますが、電子保存の場合は画面上での操作で簡単に保存することが可能です。
また紙の帳簿が必要な際には保管スペースまで足を運び必要書類の抽出作業が必要になり時間と手間がかかります。
電子的に帳簿や書類の保管がなされていれば、簡単に必要データの検索をすることができ、破棄する場合でも電子データであれば削除することが簡単です。
帳簿や書類を電子保存することは、紙での保存で必要となった印紙代や印刷代、インク代あるいは取引先への郵送費などの必要経費を削減することが可能となります。
また、ファイリングなど管理にかかる人件費やスペース費も大幅に削減できるのでコスト削減には大きなメリットになるでしょう。
紙の書類を扱う際は改ざんのリスクや破損してしまったり紛失する可能性がありますが、電子的に保存したデータであれば認証された社員のみがアクセスすることも可能になり、また外部クラウドシステムを利用することでバックアップ機能でのデータの紛失や破損なども回避できるでしょう。
【電子帳簿保存法のデメリット】
帳簿や書類を電子データ保存するためにはシステムを導入する必要があります。クラウドサービスの場合、初期費用と月額費用などランニングコストも発生します。
真実性と可視性の確保の要件を満たす必要があり、データ管理に関する基本的な知識やスキルが必要不可欠となり、慣れていない人が作業をすると必要以上に手間や時間がかかってしまうこともあるでしょう。
(参照:優良な電子帳簿の要件|国税庁 )
システム障害でサーバーがダウンしたり、端末自体が破損した場合は復旧までの時間を要したり、データそのものが消失してしまう可能性があります。
消失したデータの復元は極めて困難です。また日常的にデータのバックアップを徹底することが求められます。
電子帳簿保存法の実践的な手順とルール
実際に電子帳簿保存法を行うためのステップや使用できるルールについて解説
フリーランスが効果的かつ合法的に電子帳簿を管理する方法を提示
注意すべきポイント
電子帳簿保存法上で電子データの3区分ごとに改正された部分を以下にて紹介します。
電子帳簿保存に関する改正事項
法改正前まで帳簿や書類を電子データで保存する際は3ヶ月前までに税務署 長の承認が必要でしたが、法改正後は不要になります。
「優良な電子帳簿の要件」を満たすことで、万が一申告した内容に漏れが あった場合、過少申告加算税が5%軽減されることとなりました。
以下の最低限の要件を満たすことで電子データでの保存が可能になりました。
【システム関係書類を備え付けること】
【画面・書面に整然と形式や明瞭な状態で出力できること】
【電磁的記録のダウンロードが出来るようにしておくこと】
スキャナ保存に関する改正事項
電子帳簿保存と同様に、スキャナ保存についても承認が不要となりました。
スキャナー保存の場合、受領者が署名後3営業日以内にタイムスタンプを付 与する必要がありましたが、法改正後は不要となりタイムススタンプの付 与期間が最長2ヶ月以内に緩和されることとなります。
電子データを保存する際に「取引年月日」「勘定科目」「取引金額」など の項目を検索機能として必須でしたが、法改正後の検索機能は、「取引年 月日」「金額」「取引先」のみに軽減されます。
本人以外による原本との照合「適正事務処理要件」が必要でしたが、法改正後は不要となります。
スキャナ保存での電子記録で隠ぺいや仮装された事実があった場合には重加算税10%が課されるようになりました。
電子取引に関する改正事項
スキャナ保存同様に改正となり、売上高5,000万円以下の事業者は、税務調査等ですぐに提示できるようであれば検索要件は不要になります。
「紙への出力による電磁的記録の保存」が廃止されました。
スキャナ保存と同様に改正となり、電子取引での隠ぺいや仮装があった場合には重加算税10%が課されるようになりました。
まとめ
電子帳簿法を適用することで紙帳簿での作成、保存、管理などの手間が省け業務効率化が進むことは明らかで、法改正によりルールが緩和されている箇所もあるのでメリットになるほうが多いです。
ただ、システム導入の際の初期費用やランニングコストなどの発生や万が一データ消失に備えたバックアップをしておくこと対応策なども求められますので導入前に確認しておくことをオススメします。
また、案件獲得にはフリーランスキャリアの利用をぜひ検討してみてください。これまでの経験やスキルに応じた案件を紹介させて頂きます。