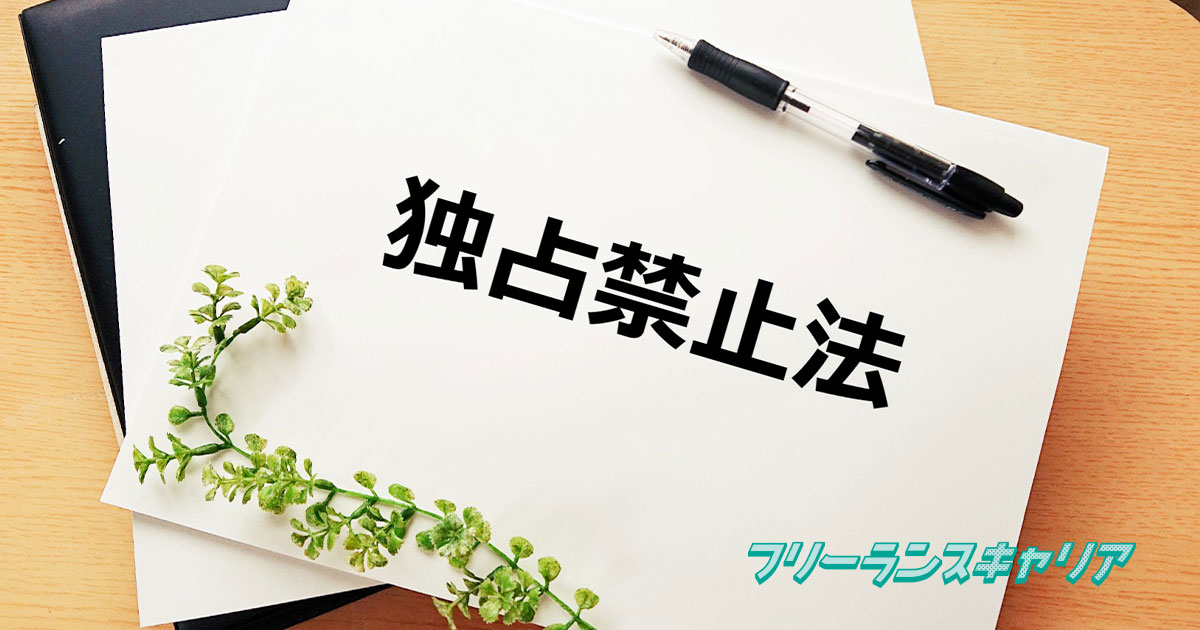「独占禁止法」という言葉を聞いたことがあるとは思いますが、その内容まで理解している方は意外と少ないかも知れません。そこで本記事では独占禁止法についての意味と内容を理解する上でフリーランスにとって重要なポイントを紹介していきます。自分の身を守る上でも必要不可欠な知識なので、理解を深めておきトラブルを回避しましょう。
そもそも「独占禁止法」とは?
独占禁止法の正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。その概要は、「公正・自由な競争を促進するために、独占や不公正な取引を禁止する」法律になります。
また、フリーランスが事業者と取引をする際には、その取引全般に独占禁止法が適用されます。さらに、相手の事業者の資本金が1,000万円を超えている場合は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」も適用されます。
フリーランスに独占禁止法が適用される背景
フリーランスの人口と独占禁止法
内閣官房の「フリーランス実態調査結果」(令和2年5月)によれば、2020年のフリーランス人口は約462万人。昨今のコロナ感染の流行もあり、今後も増えていくと考えられています。多様な働き方の一つとして、近年フリーランスに注目がより一層集まっています。フリーランスの方が安心して働き、活躍することは日本の成長の鍵でもあります。
このような状況の中、労働基準法や最低賃金法などが適用されない立場であるフリーランスを保護することは重要であり、「独占禁止法」の適用は、フリーランスとして安心して働ける環境の整備に向けた取組みの一環として、社会的満足度を高めることにつながるでしょう。
フリーランスの業務上で独占禁止法が適用になるケース

- ケース1:報酬の支払遅延
-
発注事業者の支払いが遅く、契約で決めた日までに報酬が支払われなかったり、一方的に支払日を遅く設定される場合などは、優越的地位の濫用に該当するおそれがあります。
- ケース2:報酬の減額
-
契約どおりの仕事をおこなっていたのに決めていた報酬額が支払われなかったり、業務量が増えた場合は報酬額を増やすと合意していたのに報酬額が変わらない場合などは該当するおそれがあります。
- ケース3:著しく低い報酬一方的な決定
-
発注者業者が依頼してきた価格が通常の取引時の報酬と比べて著しく低い金額であり、その価格で仕事を受けるように報酬を一方的に決定される場合などは該当するおそれがあります。
- ケース4:やり直しの要請
-
契約に基づいて仕様書通りに業務をした後で、やり直しを要請される場合などは該当するおそれがあります。
- ケース5:一方的な発注の取り消し
-
発注された仕事を進めていたにも関わらず、一方的に発注を取り消され、すでに発生していた費用が支払われない場合などは該当するおそれがあります。
- ケース6:役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い
-
発注された仕事の過程で発生した、フリーランスに属する著作権や転用可能な成果物・技術などの権利の扱いを、発注業者が一方的に決め、取り上げるなどの場合は該当する恐れがあります。
- ケース7:役務の成果物の受領拒否
-
発注業者の都合によって、成果物を受け取ろうとしない場合などは該当するおそれがあります。
- ケース8:役務の成果物の返品
-
返品の条件が不明確であるにも関わらず、一度納品した成果物を返品された場合などは該当するおそれがあります。
- ケース9:不要な商品または役務の購入・利用強制
-
業務に必要ではないのに、商品の購入を指示され、取引継続条件にされる場合などは該当するおそれがあります。
- ケース10:不当な経済上の利益の提供要請
-
協力金の負担金や、発注内容にないシステムの追加開発・デザイン作成などの契約範囲外のサービスを要請された場合などは該当するおそれがあります。
- ケース11:合理的に必要な範囲を超えた
-
発注事業者の一方的な都合で秘密保持の範囲を決めたり、発注事業者から「業務で得たスキルや知見があるから他者の仕事を受けるな」と教育コストを理由に不利な条件を提示された場合などは該当するおそれがあります。
その他の取引条件の一方的な設定・変更・実施など、取引上の地位が優越している発注事業者が、一方的に取引の条件を設定したり、取引の条件を変更したり、取引を実施する場合に正常な商習慣に照らしてフリーランスに不当に不利益を与えることとなるときは、優越的地位の濫用として問題となります。
参考:フリーランスとして安心して働ける環境を 整備するためのガイドライン(厚労省)
独占禁止法が適用対象となる範囲とは?
実際にフリーランスと独占禁止法の適用対象となる方は「業務委託契約を提携している」方です。個人で働く方、
例えば
・エンジニア
・デザイナー
・クリエイター
・ライター
・ライター
など、
企業との雇用契約ではなく「業務委託契約」を締結している方が対象となります。
優越的地位の濫用における法的規制は?
「優越的地位の濫用」に該当する場合には以下のような措置が取られる可能性があります。
・公正取引委員会の関与
・損害賠償請求、差止請求
なお、公正取引委員会が「優越的地位の濫用」と判断した場合には審査手続を開始し、排除措置命令や課徴金納付命令の措置が取られることがあります。
排除措置命令によって、「違反行為の取りやめ」「将来における同様の行為の禁止」「関係者への周知措置」「再発防止措置」などの対応が取られることが期待できます。
課徴金納付命令は、「優越的地位の濫用」行為と認められる行為を始めた日からこれを止める日までの期間(最大3年)における取引の売上または購入額の1%に相当する課税金の納付が命じられます。
また損害賠償責任は独占禁止違反と因果関係のある損害については過失がなくとも賠償しなくてはなりません。
まとめ
ここまで独占禁止法による優越地位の濫用について解説してきました。
会社員とは異なりフリーランスは労働基準法が原則適用になりません。そのため、その立場を保護するために独占禁止法により優越的地位の濫用を防いでいます。フリーランスにとって独占禁止法の知識も重要でありますが、発注者間での関係にお悩みのことがあれば、労働関係の法律の専門家などへ相談することもおすすめします。
また、自分にしっくりくる案件を探すにはフリーランスキャリアの利用をぜひ検討してみてください。これまでの経験やスキルに応じた案件を紹介させて頂きます!